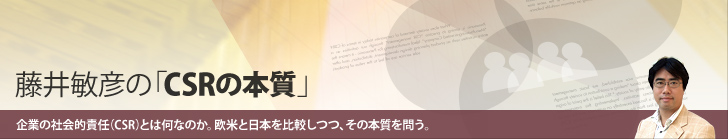(ヨーロッパの)紳士はエリートがお好き 後編
社会のシステムを大きく変えようとするとき、その時、誰がその責を担って推進役となるか、って問題なんですけどね。選挙で選ばれた政治家ですよね、普通。民主主義社会ですから。当然です。でもね、ヨーロッパっていうか、EUっていうか、ここでは少し違うんです。
2008年9月22日 10:00
(ヨーロッパの)紳士はエリートがお好き 前編
ある新聞の記者がフランスの国立行政学院の校長にインタビューした記事です。最後に校長は「もしあなたが社会に健全なるエリートが不要だと考えているのであれば、あなたとこれ以上議論しても無駄。」という趣旨の発言でインタビューを切り上げてしまいます。
2008年9月16日 10:00
日本の国際ルール交渉力
国際的ルールづくりを背負うのは誰か? 官か民かという二分法ではなく、「プロ(専門家)」だと思うのです。「プロ」が政府にいることもあれば、民間にいることもある。むしろ、理想的にはあらゆる事項について、「プロ」が民間にも政府にもいることが、その国の交渉力を支えると思います。
2008年9月 8日 12:00
人権と国家主権についてのCSR的感想文(後編) 〜 「利己的動機」の力
Andrew Moravcsik先生が論文で述べられたことは、拘束力ある国際司法裁判所を可能にしたのは、人権という概念の規範的な訴求力や民主的大国による影響力の行使ではなく、あくまで各国政府のself-interest(自己利益)に基づく「計算」であった、ということであります。
2008年9月 1日 10:00
人権と国家主権についてのCSR的感想文(前編) 〜 もう一つのヨーロッパ
友人の大学の先生がしばらく前に紹介してくれた論文がありまして、Andrew Moravcsik大先生が2000年に出した“The Origins of Human Rights Regimes: Democratic Delegation in Postwar Europe”という論文です。先週末少し時間があったのでもう一度読んでみた次第です。
2008年8月25日 11:00
真夏の夜のまじめな話:CSRと貿易ルールと企業競争力
最近、新しい本を書きつつあるのですが、その中でCSRと企業競争力の関係をもう一度考えています。キーワードにしている言葉が「ゲームのルール」。たとえば地球温暖化問題は、そのような問題が存在しなかった時とは随分と違う「ルール」を作り出しています。
2008年8月18日 10:00
アンチ・グローバリストはどこに消えた? 〜 平穏なWTO閣僚会議を考える
今回の2週間のジュネーブ出張は、WTOの閣僚会合でした。7年越しのドーハ・ラウンドを実質的に年内に妥結するためには今回、「モダリティ」と呼ばれる関税引き下げ方式に合意することが絶対条件と言われました。でも、結局それはなりませんでした。
2008年8月 4日 10:00
ヨーロッパ人が野球帽をかぶらない理由
前回まで2回続けてG8サミットを取り上げました。今回は一転、ヨーロッパ人の「かぶりもの」についてであります。えー、最初ヨーロッパに来たとき、とても意外だったことのひとつが、あまり「野球帽」をかぶっている人を見かけなかったことです。
2008年7月28日 10:00
北海道洞爺湖サミットが語るCSRのグローバルな性格
前回はNGOのキャンペーン広告を取り上げました。今回はサミットの肝である宣言文を見ることにします。CSRがサミット宣言文に登場することは、もはや特段目新しいことではありません。ただ、よく読むと、特に日本の会社にとっては傾聴すべきメッセージが入っていると思います。
2008年7月18日 08:00
G8サミット、NGO「広告」キャンペーンを読む
8年毎にまわってくるサミット主催。北海道洞爺湖サミットも無事に終わりました。今回は、メディアが報道したサミットの「記事」ではなくて、新聞「広告」を観察してみましょう。サミット初日の7月7日の日経新聞とフィナンシャル・タイムズを比べてみて面白いなぁと思いまして。
2008年7月14日 08:00
藤井敏彦の「CSRの本質」
過去の記事
- 藤井敏彦のCSRの本質的最終回:「人権」2011年5月24日
- CSRの新しい軸"Keep integrated!"2011年5月10日
- 震災の教訓を、理念に昇華しよう2011年4月 5日
- あの社のすなるCSR調達といふものをわが社もしてみむとて2011年3月 1日
- エクアドル熱帯雨林「人質」作戦が問う「エコとカネ」2011年2月 1日