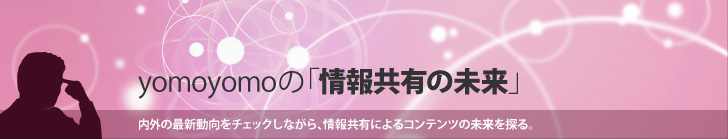敢えてブログは重要だと言いたい
先月の話になりますが、The Blogosphere 2.0 というエントリが海外で話題になりました。これはまさにブロゴスフィアの変化と最近の特徴を挙げたものです。文章の基調となっているのはブロゴスフィアの飽和と倦怠で、成熟期に入ったブログはもはや先端的なメディアではなくなったという認識です。
2009年8月11日 12:00
Eternal Principle of the Inherited Mind
『パターン、Wiki、XP』の序章は、メールやウェブ掲示板と違い「現実世界に対応するメタファ」が見つけ難い Wiki の不可思議さの話から始まります。本書は「そもそも Wiki とは何なのか?」という疑問に端を発し、それを解き明かすために建築家クリストファー・アレグザンダーという「水源」に遡ります。
2009年7月 9日 14:00
残念な日本の私
先週は、ITmedia に公開された梅田望夫氏のインタビューがワタシの観測範囲内でいろいろと話題になりました。この文章が公開される頃には新型 iPhone やらなんやらで完全に out of date な話題になっているのでしょうが、正直それでよかったと思います。
2009年6月11日 11:00
Sensorwareふたたび
以前「正念場を迎えるオライリーとEtech 2009」を書いたときに、Etech のセッション概要にやたらと「センサー(sensor)」という単語が目につくのが気になったのですが、小林祐一郎さんのブログを経由して「センサークラウド」という言葉に行き当たり、なるほどと思いました。
2009年5月14日 16:00
OpenStreetMapへの期待と課題
旧聞に属する話ですが、2月に開催されたオープンソースカンファレンス2009 Tokyo/Spring で「オープンソース地図の時代がやってくる」というセッションに参加しました。以前このブログで OpenStreetMap を取り上げたのですが、このプロジェクトについてより知りたいと思ったからです。
2009年4月 9日 14:00
正念場を迎えるオライリーとEtech 2009
TechCrunch は「“Web 2.0”という言葉は死んだ」と宣言してますが、確かにこの言葉の陳腐化は実感するところです。ただこの言葉の発案者であるティム・オライリーからすれば、カンファレンスビジネスの成否に直結する大問題で、今年は Web 2.0 Expo Europe がキャンセルとなっています。
2009年3月 4日 11:00
Jamendoな日々、あるいはWhite Light Riot賛歌
今回はクリエイティブ・コモンズライセンスで音楽をネット配信する Jamendo を紹介したいと思います。ただクリエイティブ・コモンズやフリーカルチャー周りの話は過去に何度も取り上げてきたので、今回はそれよりもこうしたネット音楽配信サービスでどのようにお気に入りの音楽を見つけるかという話をしたいと思います。
2009年2月18日 10:00
「G空間」サービスとオープンデータの行方
2007年に施行された地理空間情報活用推進基本法を受け、次世代の地図・位置情報システムを表現するのに使われ始めた言葉が「G空間」で、例えば経済産業省は「G空間プロジェクト」を掲げており、2013年までに全国レベルで3次元地図のデータベース構築を目指しているそうです。
2009年2月10日 13:00
2009年に求められるマイクロペイメントのイノベーション
昨年秋から景気の悪い話ばかりで、現実に景気が悪化しているのだから仕方ないとも言えますが、Web 2.0 の熱狂はどこへやら、広告モデルに依存したウェブサービスって生き残れないんじゃない? 無料経済なんて持続性がないっしょ、という声が強まっています。
2009年2月 4日 13:00
From Crystal Eyes To Music Dust
昔の恋人がくれたカセットテープの内容をネットで晒す極悪ブログ CASSETTE FROM MY EX を知りましたが、好きな異性にマイテープをあげるというのは洋の東西を問わない文化だったんでしょうか。この種のマイテープ、ミックステープの制作は、ウェブ時代の現在も廃れてはいません。
2009年1月28日 11:00
yomoyomoの「情報共有の未来」
過去の記事
- 1973年組の10人2011年5月12日
- HOW WE LIVE2011年4月14日
- Wikipediaがプラットフォームになるのを妨げているもの2011年2月10日
- Wikiについて語るときに我々の語ること2011年1月13日
- 自由の彼方の変わることなき独占? ティム・ウーの新刊『The Master Switch』2010年12月 9日