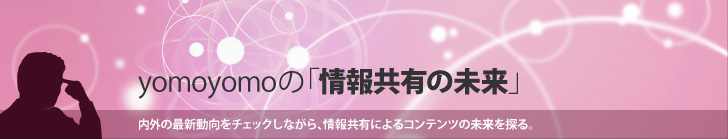1973年組の10人
足かけ5年続いた本ブログもこのフォーマットでは今回が最終回です。最後くらい個人的な事情に依った文章を書かせてください。今回はうだつのあがらないワタシが、その活動ぶりを見て励みにしている同じ1973年生まれの人たちを取り上げたいと思います。
2011年5月12日 14:30
HOW WE LIVE
地震のことはその日の朝(時差の関係)にテレビを見て知りました。前日までリビアのニュースが主だった CNN や BBC World News も、11日から24時間体制で日本を襲った震災並びに原発の話題に切り替わりました。
2011年4月14日 14:20
Wikipediaがプラットフォームになるのを妨げているもの
Wikipedia にしても問題はいろいろ抱えており、昨年末からその資金不足がバナー画像におけるジミー・ウェールズの顔のでかさにより否が応でも認知されましたが、ReadWriteWeb のエントリは、Wikipedia はウェブサービスの時代に適した「プラットフォーム」となる可能性を実現できていないと論じるものです。
2011年2月10日 14:00
Wikiについて語るときに我々の語ること
ワタシが面白いと思うのは、Wiki という言葉から人が受けるイメージ/言葉に託すイメージの相違やその変化です。ウォード・カニンガムが旅行で訪れたホノルルの Wiki Wiki シャトルバスにちなんで自身のソフトウェアを WikiWikiWeb と名付けたことに始まるわけですが、元々 Wiki とはハワイ語で「素早い(quick)」にあたる単語です。
2011年1月13日 14:30
自由の彼方の変わることなき独占? ティム・ウーの新刊『The Master Switch』
今回はティム・ウーの新刊『The Master Switch: The Rise and Fall of Information Empires』を取り上げたいと思います。重要なのは(アメリカにおける)電話・ラジオ・テレビ・映画といった分野で見られた自由から支配と独占へ向かうサイクルが、インターネットにもあてはまるとウーが論じていることです。
2010年12月 9日 15:00
オープンエデュケーションとその持続可能性
少し前に梅田望夫、飯吉透『ウェブで学ぶ ――オープンエデュケーションと知の革命』を読了したのですが、これまで何度もフリーカルチャー、オープンコンテンツを話題にしてきた本ブログのテーマにも関わる本だと思うので、今回はこの本の話から始めます。
2010年11月11日 14:30
マルコム・グラッドウェルの苦言と岡田斗司夫の予言
マルコム・グラッドウェル風に言えば、Facebook は日本でもティッピング・ポイントをこえ、アーリーアダプターの本格的利用が始まる段階に入ったと言えるでしょうか。ただ、これから一直線に Twitter は寂れて Facebook が主になる、とはワタシは思っていません。
2010年10月14日 14:30
「成功の法則2.0」と人間の多様性の証明
The Law of Success 2.0 プロジェクトは、成功を達成する万能な方法など存在しないという認識からスタートします。今回の文章を書くために、金海寛さんにメールで簡単なインタビューを行いました。その回答の力強さ、特に「僕の狙いは人間の多様性の証明にあります」という言葉に感銘を受けました。
2010年9月 9日 13:00
ウェブ時代にあるべき本の生態系を目指して
本連載を開始して三年、第1回のタイトルは「書籍とクリエイティブ・コモンズとコンテンツの未来」でした。本ブログでは何度か書籍をテーマにしてきましたが、ちょうど献本いただいた『ブックビジネス2.0』を読み終えたところなので、今回はこの本を取り上げたいと思います。
2010年8月19日 14:30
CiscoのビジネスコンテストI-Prizeと「Internet of Things(モノのインターネット)」というトレンド
日本ではあまり話題になっていませんが、Cisco が主催するグローバルイノベーションコンテスト I-Prize の優勝者が先月末決定しましたので、今回はこの話から始めたいと思います。
2010年7月 8日 14:00
yomoyomoの「情報共有の未来」
過去の記事
- 1973年組の10人2011年5月12日
- HOW WE LIVE2011年4月14日
- Wikipediaがプラットフォームになるのを妨げているもの2011年2月10日
- Wikiについて語るときに我々の語ること2011年1月13日
- 自由の彼方の変わることなき独占? ティム・ウーの新刊『The Master Switch』2010年12月 9日