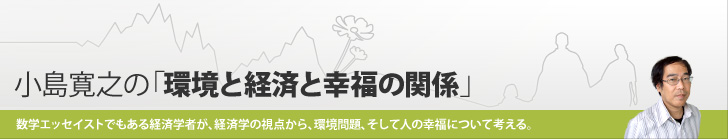環境を通じて経済をコントロールする〜社会的共通資本の理論
新年の日経新聞 論説の最後に決まって論じられたのが、宇沢弘文先生の主張する「社会的共通資本の理論」であった。今回から何回か、この理論について解説したいと思う。なぜなら、それがきっかけで経済学の道を志すことになった、それこそぼくの初心であり、いわば「縁起もの」だからだ。
2008年1月 9日 17:00
企業の有機体としての価値〜ペンローズ効果とトービンのq
前回は感覚的にだけ説明した「トービンのqが1より大きい分は、企業の有機体的な価値を表してるんだよ」ということを、ある程度きちんと数理的に裏付ける。
2007年12月28日 17:00
企業を箱ものとしてだけ見ちゃだめだよ〜トービンのq理論
M&Aに対して、日本のマスコミは、マネーゲームとか企業倫理とか職人云々の観点で語ることが多く、そうなると我々の経済「理論」の守備範囲ではない。とはいっても、数理的な経済理論のカテゴリーの中でM&Aを語るには、「トービンのq理論」が最も適切で標準的なものであろう。
2007年12月26日 11:00
いくら情報交換しても確信に至らないメカニズム〜eメールゲーム
濱野智史さんが、「情報環境研究ノート」で、コモンノレッジ(共有知識)のことを論じているので、せっかくのチャンスを逃す手はない、とばかり、ぼくもこの話を書くことにした。
2007年12月 7日 11:00
「ワリカン」システムのいたずら〜独占は「悪事」なのか?
「独占」は、「市場の失敗」である。ただ、「独占を行う企業は悪事を働いている」という風に誤解してしまいがちだ。そこで今から、「そうじゃないぞ」、ということを説明しよう。
2007年11月30日 11:00
コモンズの悲劇〜共有地とオープンアクセスの問題
「コモンズの悲劇」という見方が重要なのは、多くの環境問題にこの構造が見られるからである。例えば、地球温暖化問題がその典型といっていいだろう。
2007年11月20日 11:00
ボーナスは、モラルハザードへの対抗策なのだ〜契約理論の第一歩
一昔前、日本の企業の多くは、「ボーナス制度」を実施していて、世界的にもあまり例を見ない制度だそうだ。経済学者は、これらのシステムを、きちんとした合理性を持ったシステムだと考えている。
2007年11月14日 11:00
固定給にはそれなりの必然性がある〜リスクシェアリングの考え方
今回は、現在のメカニズム・デザインの研究の原型となったといってもいい「リスクシェアリング」の問題を扱うことにする。
2007年11月 2日 11:00
人を正直にするのは高くつくのだ〜メカニズムデザインの考え方
今年のノーベル経済学賞は、「メカニズムデザイン」という分野を樹立した3人の経済学者ハーウィッツ、マスキン、マイヤーソンに与えられた。この理論がどんなものかをがんばって解説してみよう。
2007年10月27日 22:50
2007年のノーベル賞についての雑感
今年のノーベル賞について、感じたことを書いてみたい。もともと平和賞というのは「戦略的」な色彩の強い賞であるから、その「恣意性」に異論をはさむつもりは毛頭ないのだけれど、それでも少々違和感が残った。
2007年10月18日 14:00
小島寛之の「環境と経済と幸福の関係」
過去の記事
- 最終回 バブルはなぜ起きるのか?〜バブルの合理性2008年3月31日
- バブルの何がマズイのか?〜バブルと実体経済2008年3月24日
- 貨幣のいたずら〜その多機能性が悲劇を生む2008年3月14日
- 公平とは何か〜「選択の自由」と「公平性」2008年3月 6日
- 競争が効率を妨げることもある〜過剰参入定理のふしぎ2008年2月28日