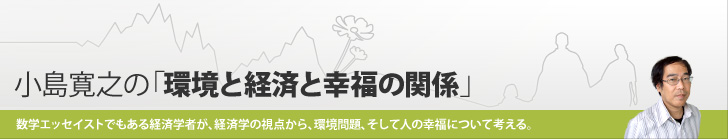第11回 株価はなぜじわじわあがって、ドーンと落ちるのか
株価の乱高下についてのとても面白い経済理論の論文を見つけたので、今回はそれをタイムリーに紹介してみたいと思う。
2007年7月31日 16:44
第9回 ケインズの「魔法のポケット」
今回からは、満を持して、ケインズ理論とその問題点について詳しく書こうと思う。まあ、できるだけショートカットで突っ走るので、投げないでおつきあいいただきたい。
2007年7月17日 02:20
第8回「多重債務に陥る人」を、経済学ではこう考える
一種の「だらしなさ」を、「人間ってだらしないよね」の一言で済ませず、経済学者たちはそこに一種の「理由付け」や「法則性」を見出そうとする。
2007年7月10日 11:00
第7回「誘惑のコスト」を環境問題に応用してみる
この評価関数が教えてくれることは、過剰消費の選択肢を抹殺するような政策を施行したほうがひょっとすると社会にとってより良いかも、という視点である。
2007年7月 3日 01:00
第6回「誘惑」の経済メカニズム
誘惑がコストとして働くことや、人がそれに打ち勝ったり負けたりすることを、従来の経済学ではうまく説明できないでいた。ところがつい最近、その困難が突破されたのである。
2007年6月26日 01:00
第5回 ライアーゲームっていうのは、要するに協力ゲームなのだ
今回はうってかわって、テレビドラマの話。今期のドラマの中で出色だったのは、「ライアーゲーム」である。すぐにドラマのストーリーそのものに引き込まれてしまった。それは、この物語が、まるで経済学における「ゲーム理論」を体現していたからだ。
2007年6月19日 12:46
第4回 『不況のメカニズム』は、いかにすごい本か
最近出版された本、小野善康『不況のメカニズム』が、いかにすごい本であるか、そして、いかにぼくにとってショッキングであったかをもうちょっとお話ししようと思う。
2007年6月12日 01:08
第2回 「環境にやさしい」は、めぐりめぐって自分の損になる
環境と経済にはある種のトレードオフが存在している。そのトレードオフを覚悟の上で、できるなら災いへの処方箋も携えながら、ぼくらは清らかな地球だかに、向かうべきなのだ。
2007年5月29日 00:56
小島寛之の「環境と経済と幸福の関係」
過去の記事
- 最終回 バブルはなぜ起きるのか?〜バブルの合理性2008年3月31日
- バブルの何がマズイのか?〜バブルと実体経済2008年3月24日
- 貨幣のいたずら〜その多機能性が悲劇を生む2008年3月14日
- 公平とは何か〜「選択の自由」と「公平性」2008年3月 6日
- 競争が効率を妨げることもある〜過剰参入定理のふしぎ2008年2月28日