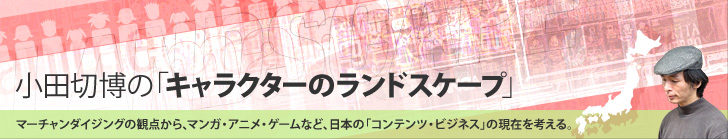民主党政権誕生と知的財産戦略本部
8月末の衆議院選挙は民主党の歴史的な大勝利となり、与野党は逆転、鳩山新政権が誕生した。この結果を受け、民主党がたびたび批判してきた「国立メディア芸術総合センター」建設は白紙化されることになったようだが、政府によるコンテンツ産業振興策や文化政策そのものはどのような影響を受けるのだろうか。
2009年9月25日 14:50
「マンガ研究」ってなに?
「何をやりたいか」によって必要な情報は異なる。たとえば大友克洋とメビウスの比較論をやりたいなら、メビウスやその背景となるフランスのコミックス事情について知らないのは単に致命的だが、大友克洋を論じるために必ずメビウスを引き合いに出さなければならないわけではない。
2009年8月25日 14:00
なぜ「収集・保存」なのか?
ようやく衆議院が解散し、民主党政権誕生の可否が問われる選挙を控えて「国立メディア芸術総合センター」を巡る動きが活発だ。相変わらず混乱しているとしか思えない状態だが、文化庁としては選挙で民主党が政権をとった場合の予算凍結を恐れ、なんとか建設を既成事実化しようという意図があったのだろう。
2009年7月28日 13:30
「国立メディア芸術総合センター」に関する混乱
2009年6月に入ってから「国立メディア芸術総合センター」を巡る議論が白熱している。ネット上でも多くのひとたちが賛否を論じているが、ここではこの問題に対する賛否ではなく、わかったようでよくわからないこのニュースに関する問題の整理と切り分けを少し試みてみたい。
2009年6月23日 13:00
「デジタルコンテンツ」と「メディア芸術」
「メディア芸術祭」も「デジタルコンテンツグランプリ」も、年一回「アート」「エンターテインメント」「アニメーション」「マンガ」の4部門の作品、クリエイターに対し賞を授与するものだ。このふたつはどこが違うのかがまるでわからない。
2009年5月26日 14:00
龍珠狂想曲(ドラゴンボール・ラプソディ)
話題作だけあって経緯のほうも割りと日本語のニュースになっているが、公開もされ興行収入の結果も出てきてる現在、時系列に沿ってその辺を振り返ってみるのも、今後日本のキャラクター文化を考えていくためにはいいんじゃないかという気がする。
2009年4月28日 14:00
コンテンツはどこから来たか
もうほとんど忘れ去られていることのような気がするが、「コンテンツ」というのは日本社会においては90年代も後半になってから一般化した言葉である。実際に過去の新聞報道での用例を追ってみると、このことははっきりわかる。
2009年3月24日 15:00
マンガと海外
レポーターの報告では日本マンガの海外への影響はさかんに語られるのに、その海外(アメリカ、アジア、ヨーロッパ)におけるマンガのあり方や状況に関してはほぼ触れられず、現に存在している海外「から」の影響もほぼ無視される、という態度が一貫してとられていた。
2009年2月27日 14:00
プロパティーという考え方
最近、会話をしていて何度か「プロパティーってなに?」と聞かれた。特になんにも考えずにしゃべっていたので、逆に「これってそんなにわかりにくい概念だったのか」とか思ったのだが、プロパティーというのは「property」と表記するアメリカの法律用語で「所有権、使用権」を意味する言葉である。
2008年12月 9日 08:30
点と線
去る2008年11月11日、今年6月にマンガ家の雷句誠が自身の作品の出版元である小学館に対し、貸与していた原稿のうちカラー原稿5枚を紛失したことに対して損害賠償を求めて起こした提訴が被告である小学館側が過失を認め、謝罪と255万円の和解金の支払いをすることで判例としては「和解」のかたちで決着した。
2008年11月18日 13:50
小田切博の「キャラクターのランドスケープ」
過去の記事
- 「クールジャパン時代」の終わり2011年5月25日
- 「わからない」という出発点2011年4月27日
- ヒーローはいつも間に合わない2011年3月22日
- ある「共感」2011年2月22日
- エロと暴力のマンガ、アニメ2011年1月26日