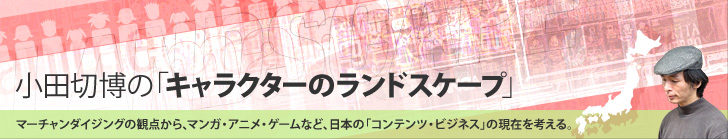ある「共感」
2011年2月22日
(これまでの 小田切博の「キャラクターのランドスケープ」はこちら)
先月、つまり2011年の1月に、アメリカの大学でコミックス研究をしているちょっと変わった日本人研究者、鈴木繁が日本に里帰りしていて、マンガ学会の海外マンガ交流部会の主催で彼の話を聞く小規模な集まりがあった。
私は鈴木と2009年末に京都でおこなわれた国際学術会議「世界のコミックスとコミックスの世界――グローバルなマンガ研究の可能性を開くために」(鈴木と私の論考を含む、この時の発表を元にした論集が現在ダウンロードできる)で知り合った。以来、国内のマンガ研究者、批評家に対してはほとんど抱くことのないタイプの共感を勝手に持っている。
この「共感」は「自分の抱く問題意識が周囲の無関心によって問題意識としてすら理解されない」とでもいうしかない体験の有無によるものである。
ここでもこれまで何度か似たようなことを書いているが、私は国内の批評家や研究者に対し、「海外のコミックスに関してじつは知らないし、関心すらないまま発言をしているのではないか」といい続けてきた。鈴木とはじめて話したときにわかったのは、彼がこれとほぼ逆方向の苦闘、つまり「アメリカで日本におけるマンガ言説の文脈を知らないまま語られる日本マンガ論への問題提起」を必然的に強いられてきた、ということだった。
つまり、日本人は日本人の、アメリカ人はアメリカ人の常識や自明性に基づいて「マンガ」なり「コミックス」を語り、そのことになんの疑問も抱いていない。私は日本でアメリカンコミックスを語ろうとすることで、鈴木は逆にアメリカで日本マンガを語ろうとすることでこの「常識」自体に疑問を抱き、結果的に周囲とコンフリクトを起こすことになった。
このコンフリクトがストレスフルなのは、自分の持つ問題意識が他の人間にとっては自明とされる事柄に関するものであるために、多くの場合「なにが問題なのかわからない」という反応をされてしまうことである。そのためその問題意識を相手に理解してもらうためには遠回りになっても、なぜそれが「当たり前」ではなく、疑問に思うべき事柄なのかを相手に説くところからはじめねばならない。
そのため「コミックス」って何? 「マンガ」って何? といったことを「なぜ疑問に思わねばならないのか」というレベルから論じざるを得ず、こんなしちめんどくさいことは、誰だってやりたくはないのである。
しかし、そこからはじめなければ話が通じないのだからそこからやる以外ない。
私が鈴木に対して抱く「共感」は、おそらく彼にとっては迷惑なことだろうが、この私自身の「めんどくさいことを仕方ないから(嫌々)やっている」感覚と共通するものを彼の発言から感じたことが大きい。
飽くまで私見だが、こういうレベルの試行錯誤、根本的なレベルの疑問、問題意識を持って「マンガ」というメディアについて発言してきた研究者、批評家は、日本国内においては二人くらいしかいない。常に海外コミックス紹介の最前線に位置し続けてきた小野耕世と、外国人マンガ研究者として日本で研究活動をおこなってきた前述の国際会議の企画者でもあるジャクリーヌ・ベルントだ。
その意味で小野の著作の多くが現在入手困難であることやベルントの主著『マンガの国ニッポン』がマスコミレベルではあまり話題にもされてこなかったことは、現在の日本のマンガ言説のあり方のある側面をはっきりあらわしているように思う。
70年代以降の日本の「マンガ批評」は、一般読者向けのバイヤーズガイド、ブックレビューとして発展してきたものであり、読者との共通体験としての「マンガのおもしろさ」を語り合うためのものである側面を強く持っている。そこではほぼ常に「自分達にとっておもしろい作品について楽しく語り合うこと」がまず第一に希求されてきた。多くの場合そのために都合の悪い事実や問題提起は無視され、場合によっては積極的に攻撃され、排除されることすらある。
小野やベルントの業績に対する認知が積極的な排斥によるものだとは思わないが、そこに消極的な無関心があることは確かだろう。
しかし、80年代以降の国内のマンガ市場の巨大化によって、個々の読者にとっての「マンガ」が共通体験ではありえないものになり、海外でのマンガ人気といった現象の影響もある現在、これまで棚上げにされてきた「マンガ」に関する多くの疑問点が徐々に「問題化」されつつあるとも私は考えている。
要は「知らないこと」、「わからないこと」、それが「共通体験」ではありえないことを前提にしなければ、自国のものであれ他国のものであれ、「マンガ」について語り合うことそのものがもはや困難になっているのではないかと思うのだ。
タイムリーなことに1月の集まりを主宰した海外マンガ交流部会も3月6日に京都国際マンガミュージアムにおいて「そもそも『海外マンガ』とは何か!?――グローバル化するコミックス事情の最前線」と題したイベントをおこなう事になっている。なによりも鈴木のような海外で活動する日本人研究者の存在自体が、そのような状況の変化を雄弁に物語るものだといえる。
私自身の問題提起が多少なりとも認知され、関心を持たれるようになったこともそうした背景があってのことだとも考えているのだが、今後そのような疑問を持つことが一般的なことになっていけば、今度はそれが「他人から理解されない疑問」だったことのほうは急速に忘れ去られていくだろう。
そのこと自体はいいことだと思うが、私が鈴木や小野、ベルントのようなひとたちに抱くこの一方的な「共感」は、そうなったらそうなったで若い研究者たちにはまったく理解できないものになっていくのだろうとも思う。
......なんか損したような気分にならないこともない。
小田切博の「キャラクターのランドスケープ」
過去の記事
- 「クールジャパン時代」の終わり2011年5月25日
- 「わからない」という出発点2011年4月27日
- ヒーローはいつも間に合わない2011年3月22日
- ある「共感」2011年2月22日
- エロと暴力のマンガ、アニメ2011年1月26日