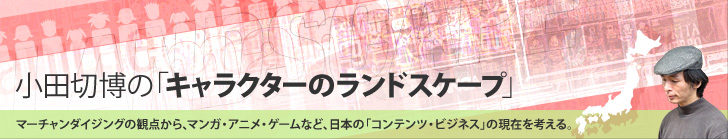「自明性」をめぐって
……で、なんでまたこんなしち面倒くさいことを考えているのかというと、じつは先日著者の方から送っていただいた『ハルヒ in USA』(三原龍太郎、NTT出版刊)という『涼宮ハルヒの憂鬱』の北米での展開についての研究書が、ここまで書いてきたようなことに引っかかって全然読み進めないためだ。
2010年7月27日 14:00
揺れる言葉
2000年代アメリカにおけるコミックスに関する「批評」のアンソロジー『The Best American Comics Criticism』。巻頭の編者ベン・シュワーツによる序文にはちょっと興味深いエピソードが書かれていた。それはシュワーツが書店のコミックス売り場で目にした十代の少女二人の会話である。
2010年6月29日 14:00
コンテンツ産業とキャラクタービジネス
本来の定義や用法が参照されないまま、なぜか「コンテンツ産業」という概念が「アニメやマンガ」と無造作に結びつけて語られてしまう、現在のマスメディアやネットにおける言説のあり方自体が問題なのだと思っている。
2010年5月25日 14:00
自戒と韜晦
2009年1月に京都の国際マンガミュージアムでおこなわれた同名のシンポジウムをベースに編まれた論集『マンガは越境する!』に収録された小野耕世「増殖するマンガ」というテキストを読んで、ひどく複雑な気分になった。
2010年4月28日 14:30
マンガとイラストレーション
ちょっと事情があって、ここのところ60年代末から70年代初めごろに出版された石子順造や鶴見俊輔、尾崎秀樹などの書き手による日本のマンガ論の類を読み漁っている。中でも読んでいて発見が多かったのが、草森紳一の『マンガ考』。海外コミックス紹介史の観点から見ても興味深い。
2010年3月23日 14:00
売れる、売れない
昨年みすず書房から発売されたアラン・ムーアとエディ・キャンベルの『フロム・ヘル』の翻訳単行本が順調に版を重ねている。映画の公開もあってロングセラーになった『ペルセポリス』の話題とあわせて、最近友人のマンガ評論家・伊藤剛と話をしていたとき、その辺の海外コミックスの好調が話題に上った。
2010年2月23日 12:00
本のタイトル
年初にちくま新書から『キャラクターとは何か』という本を出していただいた。ここで書いてきたことをベースにして書いた本なので、こちらの読者の方にはよろしければ手にとっていただきたいと思う。
2010年1月26日 14:30
間抜けな話
私事で恐縮だが、前回の記事でも少し触れたように12月17日から20日まで京都国際マンガミュージアムでおこなわれた国際学術会議で、マンガ評論家の夏目房之介、ベルギーのマンガ研究者、パスカル・ルフェーブルの2氏との「グローバル化における越境とマンガ研究」と題するセッションに参加してきた。
2009年12月22日 15:00
「マンガの国際学術会議」が日本で開かれる意義
先日出版されたティエリ・グルンステン『マンガのシステム コマはなぜ物語になるのか』の訳者である野田謙介と話していて、日本と欧米の「マンガ」に関する市場認識の違いについての話題になった。日本では依然として海外のマンガは日本マンガと無関係なもののように扱われ続けている。
2009年11月24日 14:00
「ポップ」がわからない
以前、マンガ評論家の伊藤剛と話をしていて「小田切さんはポップがわかるから」といわれて唖然としたことがある。「最近の若いヤツはポップがわからないから話が通じない」というようなことをいいたかったらしい。そこで私が思ったのは「ポップがわかる」ってどういうことだろう?ということだった。
2009年10月27日 14:30
小田切博の「キャラクターのランドスケープ」
過去の記事
- 「クールジャパン時代」の終わり2011年5月25日
- 「わからない」という出発点2011年4月27日
- ヒーローはいつも間に合わない2011年3月22日
- ある「共感」2011年2月22日
- エロと暴力のマンガ、アニメ2011年1月26日