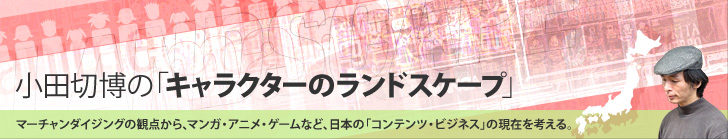間抜けな話
2009年12月22日
(これまでの 小田切博の「キャラクターのランドスケープ」はこちら)
私事で恐縮だが、前回の記事でも少し触れたように12月17日から20日まで京都国際マンガミュージアムでおこなわれた国際学術会議で、マンガ評論家の夏目房之介、ベルギーのマンガ研究者、パスカル・ルフェーブルの2氏との「グローバル化における越境とマンガ研究」と題するセッションに参加してきた。
そもそもこのお話をいただいた時には、学者としての肩書きがあるわけでも、特に知名度が高いわけでもない私になぜこんな話がきたのかさっぱりわからなかったのだが、事実上このイベントのプロデューサー兼ディレクター役を果たした京都精華大学のジャクリーヌ・ヴェルント氏(私たちのセッションの司会役でもあった)から直接その意図を聞いた際に、その理由に深く納得して二つ返事でお受けすることにした。
それは「たしかにそんなことは他のひとには頼めないだろうし、どう考えても頼んだところで断られるだろう」と思うしかないような理由だったのだ。
今回私にしては珍しく、その「依頼された仕事」をほぼ完璧に果たしたという自負を持っているのだが、実際におこなわれたセッションの具体的な内容についてはここでは触れない(というかあんなもの、仮に詳細に文字起こししたところで伝わるわけがない)。
ここで書いておきたいのは、この会議で経験したある些細で間の抜けたエピソードについてである。
じつはこの会議を初日から聞いていて、ひとつ怪訝に思ったことがあった。
若い日本人研究者の発表や報告で、やたら「小田切博」の文章が引かれていたのだ。これは自慢話めいて聞こえるだろうし、もちろんそう取ってもらってかまわないのだが、じつは私自身は彼らの発表を聞きながら「アカデミックなマンガの研究発表の場で夏目房之介や大塚英志、伊藤剛なんかじゃなくてオレの文章が引かれるって変なところだなあ」などと思っていた。
しかし、会期中に(彼自身は会議での発表者ではないのだが)ある若い研究者と彼の書いた論文について話していて「なんであんなにオレの文章ばっかり引いてるの? あんなことオレしかいってないじゃない」「いや、小田切さんしかいってないから引いてるんですが」というきわめて間の抜けた会話をして「ああ、そうか、日本でオレしかいってないからオレから引くしかないのか」とその理由には気がついたのだが、依然として納得がいかなかったのは、彼ら若い研究者たちは私と違いアカデミックな専門教育と訓練を受け、自分なりに自分の現場でそうした問題意識を育ててきたことがあきらかなひとたちばかりだったからだ。
正直いって「だったら特に読まれてるわけでもないオレの言葉なんか引かずに自分の言葉で語ればいいのに」と思った。
私自身はここ十年ほど「日本マンガや文化の特殊性もしくは優位性を主張したいのなら、具体的な比較検討を通しておこなうべきだ」という個人的には自明だとしか思えない指摘をおこなうために個別の事例ごとにいちいち具体的な説明をする、というきわめて不毛な作業を繰り返してきた。おかげで私はやたらと攻撃的に見えるらしいのだが、本当は本人だってそんなめんどくさいことはやりたくはないのである。いちいち説得や説明をする必要なくスムーズに話が通じるならそのほうがいいに決まっている。
だから、社会学や歴史学、美術史、カルチャラルスタディーズなどのアカデミックな現場で具体的な問題意識を育てた彼ら若い研究者たちに出会い、彼らになんの違和感もなく自分の問題意識が「問題」として共有される場面に出会って、私はほとんどカルチャーショックに近いものを受けた。自分が孤独ではないことをはじめてそこで実感として知ったのである。
さらにもうひとつ間抜けな話を書いておけば、先に無造作に「孤独」と書いたが、私はつい最近まで自分が「孤独だ」とは考えていなかった。「自分しかそう考えていない」という状況が当たり前すぎて、それになにがしかの形容を与える必要を感じなかったのだ。
少し前、2007年に出した『戦争はいかに「マンガ」を変えるか─アメリカンコミックスの変貌』というアメリカンコミックスについて本の担当編集者と最近の日本での海外コミックスの紹介や研究状況に関する話(というよりそれに携わるひとたちにまつわる世間話)をしていて「よかったじゃないですか、あの本書いてた頃みたいなひとりで孤独にコツコツやってる感じじゃなくなってきて」といわれたのだが、そのときはじめて「ああ、アレは『孤独』というものだったのか」と気がついたくらいである。
おそらく大多数の読者にはどうでもよいことだろうが、このような訳でこの会議は私にとってはきわめて感動的な体験だった。そこで、会うひと毎にその感動を語り、そのうえで「しかし、なんでオレの言葉を引くのかね?」と疑問を呈していたら、複数のひとから呆れられた。彼らは「おまえ自身がそういうことを感じるんなら、似たような問題意識を育ててきた彼らがお前のテキストからある種のカタルシスを得るのは当たり前じゃないか」というのだ。
そういわれれば「そうかな」という気もするが、一方でやはり「べつにオレの名前や言葉を引いたところで得なこともないだろうに」とも思う。
まあ、損得の問題でもないわけだが。
小田切博の「キャラクターのランドスケープ」
過去の記事
- 「クールジャパン時代」の終わり2011年5月25日
- 「わからない」という出発点2011年4月27日
- ヒーローはいつも間に合わない2011年3月22日
- ある「共感」2011年2月22日
- エロと暴力のマンガ、アニメ2011年1月26日