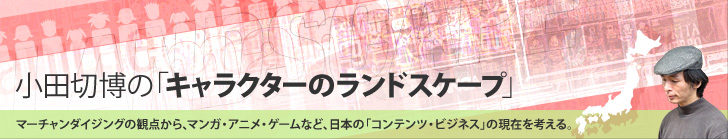「自明性」をめぐって
2010年7月27日
(これまでの 小田切博の「キャラクターのランドスケープ」はこちら)
最近「自明性」ということについて考える……というよりは、それを「問題にせざるを得ないのではないか」と感じてしまうことが多い。
なんだか知らないが、漠然と「これって当然そうでしょ」と思われていることを調べてみたら「じつは全然そういうことではなかった」という事例につきあたったり、「こんなの普通知ってるよね」的な態度でいわれていることに対して「そんなの説明されなきゃ絶対わからねえ」と思ってしまったりすることがやたら多いのである。面倒くさいから私だってそんなことに突っ込みをいれたくはないのだが、そういう場合、どうもまずそこを問題にしないと話が通じない気がする。
先日これと似たような感覚について千野帽子が、日経ビジネスオンラインのコラム「「わかってる/わかってない」で世界を分割する人たち。」で書いているのを読んだ。しかし、私の感じる違和感というか不自由さはここで千野の書いているものともどうやら違っている。
私はそのモノなりコトなり問題なりを自分が「わかって」いようが「わかって」いまいが、そのこと自体はどっちだっていいのである。
自分が知ってることなど既に知っていることに過ぎないのだし、知らないことは知らないんだから他人に聞くなり調べるなりすればいいだけの話だ。千野も指摘するように「わかってる/わかってない」という分割自体は問題ではない。
ただ、そこで千野のいうように「「わかってない」自分を、認め」ても、私の場合は苛立ちが募るばかりでなんの解決にもならない。そもそも私が感じている不自由さは、個人や社会によって無意識にある物事を「わかってる」ことが前提とされているために「話が通じなくなる」こと、相手とのコミュニケーションの部分にあるからだ。
実際のところ(本当は誰でもそうだろうと思うのだが)誰かと話をしていて、私自身「わかってる」立場に立つこともあれば「わかってない」立場に立つこともある。どちらの場合であっても、一番問題にするべきなのは相手と話を通じさせることだろう。自身が「わかってる」側であれば相手にわかるようにそのことを説明しなければならないし、逆に「わかってない」のなら何がわからないかを相手にキチンと伝えられないと話にならない。
そういう場合に考えるべきなのは、自分がどっち側かなどということではなく、相手や自分、もしくは社会的にそれがどのようにわかられ、あるいはわかられていないかという部分、要するに対象とする物事をどう定義するか、である。
もちろんこの場合の「定義」は一般的な公理のようなものではなく、相手とのあいだで話題となっている概念についての適当な共通認識程度のものだが、自分自身であれ、相手であれ、どちらかがそのような共通認識を築く努力を厭ってそれを「知っていることが自明」なものとして話をしてしまうと通じる話も通じなくなってしまう。
それでも対面で話をしているような場合は、その場のやりとりの中でそのような認識の齟齬や不明点を互いに埋めていけばいいだけのことだが、問題なのはここで現在私自身がおこなっているようにある程度公に向けて文章や談話を発表する場合である。
この場合、自分が書くすべての事柄をテキスト内でいちいち定義しておくことが不可能である以上、ある程度は「一般的に知られている」ことを期待し、自明のものとして扱う部分を残さざるを得ない。
以前、アメリカンコミックスについての本を出したあとに、友人から「アメリカのコミックス事情については執拗に説明してあるのに対して、むしろ日本マンガについて用語などの説明が足らない」との指摘を受け、その指摘自体には「もっともだ」と納得したのだが、一方で「とてもそこまではやっていられない」とも本音の部分では思った。あきらかに知られていない(しかも自分自身さほど理解していない)と思われる部分について説明を加えるのが精一杯で、国内マンガについてはある程度共通認識が確立されているだろう、と期待して放置した部分はあったからだ。
その後、具体的に国内のマンガ言説を過去に遡って追ってみて、この「期待」自体がまったく甘く「マンガについての確立された共通認識」などというものはじつはほとんど存在していないのではないか、と個人的には考えるようになったのだが、それでも人間は全知であることなど不可能であり、紙幅も限られる以上、そのような「自明」なものとして残される部分はテキスト内にどうやっても生じざるを得ないだろうとは思っている。
つまり、まったく注釈なしで誰が読んでも100%内容が理解できる文章など書きようがない。ならば、書き手が書き手としてまず意識すべきなのは「そのテキストの読者が大雑把にどのような傾向を持つか」ということと、その上で「そのような読者に対してそのテキストの内容を伝えるために説明が必須となる部分はどこにあるか」の二点になるだろう。
誰に向けて書くかによって説明すべき事柄は異なるし、なにを伝えたいかによっても説明の必要性は高くも低くもなり得る。
にもかかわらず、私自身を含めて書き手は往々にして「開示すべき情報」の基準点や内容を読者ではなく自己の側に置きがちである。
無論、そのテキストの読者を完全に確定などできないのだから、実際に読んだ個々の読者の感覚とズレが生じるのは仕方がない。しかし、少なくともこうした「自明性」に関する読者とのあいだの感覚の違いは書き手によって常に意識されるべきものだろうと思う。
……で、なんでまたこんなしち面倒くさいことを考えているのかというと、じつは先日著者の方から送っていただいた『ハルヒ in USA』(三原龍太郎、NTT出版刊)という『涼宮ハルヒの憂鬱』の北米での展開についての研究書が、ここまで書いてきたようなことに引っかかって全然読み進めないためだ。
この「引っかかり」は「私が読者でなければ感じないものではないか」と思われる部分もけっこうあるのだが、どうもそれだけでもない。
この本は三原がアメリカの大学院に提出した修士論文をもとにしたもので、もともとはアメリカのアニメ研究者向けに英語で書かれたものだ。それが著者自身の手で日本語の著作としてリライトされているわけだが、どうも北米の研究者にとって自明なことと日本のアニメファンにとって自明なことがそれぞれ説明がないまま混在して使われており、読んでいると混乱してしまう。
たとえば三原は「北米のアニメファン」と無造作にいい、それを「日本のアニメファン」と比較しているのだが、個人的にはそのような比較自体に無理を感じる。日本語でアニメファンといった場合、ジブリ映画の観客やポケモンの映画に集まる子どもたちなどまでを含むかなり広い範囲の集合になるのではないかと思われるが、北米における日本アニメのファンはそれに対応するような大きな集合ではない。北米において日本での「アニメファン」に当たるのはディズニー映画やアメリカ産のものまで含むテレビアニメーション全体のファン、観客になるはずであり、特に日本アニメを好む層はその中のひどく限られた一部に過ぎない。その限定された一部を日本における全体と対比するのは本来無理な話なのではないか。
ひどく詳細に既存の学問的文脈の中での自身の意義性が謳われているこの本には、そもそも「アニメ」とは何か?ということを含めた、そうした根本的な部分での概念の定義、共通認識の擦り合わせをおこなおうという意識がなぜか希薄である。
こういうものに出会うたびにどうしても私は「これで話が通じるんだろうか?」と首を傾げたくなってしまう。
小田切博の「キャラクターのランドスケープ」
過去の記事
- 「クールジャパン時代」の終わり2011年5月25日
- 「わからない」という出発点2011年4月27日
- ヒーローはいつも間に合わない2011年3月22日
- ある「共感」2011年2月22日
- エロと暴力のマンガ、アニメ2011年1月26日