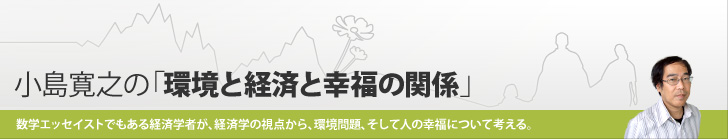最終回 バブルはなぜ起きるのか?〜バブルの合理性
このブログの最終回にあたる今回は、「災厄」であるバブルが、どうして起きるのか、そこに何らかの合理性はあるのか、それを考えてみることにしよう。
2008年3月31日 09:00
バブルの何がマズイのか?〜バブルと実体経済
「バブルがはじけるとなぜ不況になるのか?」この問題は、ぼくの知る限りにおいて、経済学の教科書できちんと説明しているものはなく、また定番的な学説もないようだ。したがって、今回、展開するのは、全くのぼくの持論であることをお断りしておく。
2008年3月24日 01:00
公平とは何か〜「選択の自由」と「公平性」
世の中で公平を生み出す方法は、大きくいって二種類ある。一つは、完全な確率的対称性を利用することであり、もう一つは「選択の自由」を保証することである。同じ公平性の創出の手段であるにしても、この二つの方法は似て非なるものといっていい。
2008年3月 6日 11:03
競争が効率を妨げることもある〜過剰参入定理のふしぎ
前回は、経済学者・鈴村興太郎の論を借りて、「競争の本当の意義は何だろうか」ということをまとめた。今回は、鈴村&清野の「過剰参入定理」を利用して、その論を深めることとしよう。
2008年2月28日 10:00
競争はそれ自体に価値がある〜「競争」と「自由」
経済社会について語られるとき、必ず登場するのが「競争」である。その多くは、「競争は社会を良くする」、という文脈で語られる。しかし、「なぜ競争は良いことなのか」、ということの答えは一枚岩ではなく、さまざまな答え方がある。このことについて、改めて愚直に問い直してみたいと思う。
2008年2月20日 00:00
環境こそが経済を最適化する〜公共財と限定合理性
ここのところずっと宇沢弘文の提唱する「社会的共通資本の理論」をいろいろな角度から紹介して来た。今回は、その仕上げをしようと思う。
2008年2月12日 16:00
学校は何のための装置か〜教育をめぐる経済学
このところずっと、経済学者・宇沢弘文が提唱する「社会的共通資本の理論」のことを解説している。今回は、「学校教育」という社会的共通資本についての宇沢の考えを紹介することとしよう。
2008年2月 4日 16:00
魅力的な都市とは〜ジェイコブスの四原則
社会的共通資本を制御する装置としての「都市」をどう設計するのがいいか、そのような問題が未解決なのは、経済学がいまだに成熟の途にあることの証拠であり、身内のひいき目でいえば、経済学の新しい可能性のありかを示しているのである。
2008年1月24日 01:00
お金より環境でしょ〜社会的共通資本とミニマム・インカム
宇沢弘文は「社会的共通資本の適切な供給と配分によって、自由競争市場社会よりもより人間的でより快適な社会を作ることができる」、と主張する。これは、環境についての、全く新しいポジティブな捉え方なのだ。
2008年1月17日 01:00
小島寛之の「環境と経済と幸福の関係」
過去の記事
- 最終回 バブルはなぜ起きるのか?〜バブルの合理性2008年3月31日
- バブルの何がマズイのか?〜バブルと実体経済2008年3月24日
- 貨幣のいたずら〜その多機能性が悲劇を生む2008年3月14日
- 公平とは何か〜「選択の自由」と「公平性」2008年3月 6日
- 競争が効率を妨げることもある〜過剰参入定理のふしぎ2008年2月28日