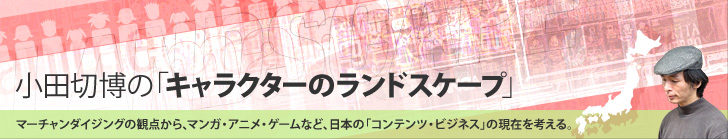「クールジャパン時代」の終わり
マンガにしろアニメにしろ、今後も日本社会の中で数多くつくられ消費されていくだろう。だが、それらの存在がここ10年ほどの日本社会で語られてきたように、ストレートに「国力」と結び付けて語られるような状況はもう存在し得ないはずだ。
2011年5月25日 14:30
「わからない」という出発点
今回の震災に関しても多くのデマや誤解が各所で生じている。メディアにかかわる人間であっても、なにか事件や災害が起こった際にその問題に関する知識を持っているかどうかは不確定である。知識の偏差に対してどう対処すればいいのか、といえば、まず自分が「わかっている」という前提に立たないことだろう。
2011年4月27日 14:30
ヒーローはいつも間に合わない
チェルノブイリ原子力発電所の事故は、東日本大震災の渦中にあるいまから25年前、1986年4月26日に起きた。それから1年が過ぎた1987年、『Justice League』誌で、バットマンをはじめとするスーパーヒーローたちがロシアの原子力発電所の危機を救おうとするストーリーが展開されている。
2011年3月22日 12:30
ある「共感」
アメリカの大学でコミックス研究をしているちょっと変わった日本人研究者、鈴木繁とはじめて話したときにわかったのは、彼が私とほぼ逆方向の苦闘、つまり「アメリカで日本におけるマンガ言説の文脈を知らないまま語られる日本マンガ論への問題提起」を必然的に強いられてきた、ということだった。
2011年2月22日 14:30
エロと暴力のマンガ、アニメ
年頭に現代美術のアーティストである村上隆とアニメーターの北久保弘之がTwitter上で論争的なやりとりをしていた。私見では、北久保側の認識は自分たちのつくっているものの性質についても無自覚すぎるように思われる。それは村上がプロデュースしてきた作品は、欧米での日本マンガ、アニメ観を反映したものでもあるからだ。
2011年1月26日 14:30
「ぼくら」の再生産
批判しているポイントこそ異なるものの、伊藤も私も70年代後半から80年代にかけてのマンガ言説を「マンガ言説が変質していく転換点」と考える点ではほぼ共通していた。しかし、私は最近日本における過去のマンガ言説を具体的に追っていく中で、自分のこの考えは誤っていたのではないかと考えはじめた。
2010年12月22日 14:30
「マンガの神様」からの宿題
手塚治虫の生前最後のインタビュー集として石子順を聞き役とした『漫画の奥義 作り手からの漫画論』という本がある。手塚は「漫画の世界はそんなに漠然としたものではなく、もっと範囲も狭いし、非常に限定された世界の中で、限定された作品が生まれているものなのです」と指摘している。
2010年11月24日 13:30
引用の効能
ちょっと前に、ある大学の先生がネットから抜書きしただけの学生のレポートに怒っていたので「引用の仕方がわからないんじゃないか」といったら「そのくらい教わらなくてもわかって当然だ」といわれた。しかし、個人的にはこれはけっこう疑問である。
2010年10月26日 13:30
2010年の「911」
アメリカのTVアニメ『サウスパーク』のムハンマドを登場させた回の放映が自粛されたことを皮肉って、「今日をムハンマドを描く日にしよう」と登場人物に語らせるマンガを描いたマンガ家が、本当に「ムハンマドを描く日をつくろう」と主張するFacebookのコミュニティーが立ち上げられたことによって、(この動きにこのマンガ家自身は関わっていないにも関わらず)尖鋭的なイスラム教徒から暗殺予告を出され、結果的に身を隠さざるを得なくなった。
2010年9月28日 15:00
大人向け、子ども向け
たとえば仮面ライダーの変身ベルトはそのCMを観れば過去から現在に至るまであきらかに男子児童向けの玩具なわけだが、現在ではこれをコレクションする「大人」のマニアが存在することは(特に正統化が必要とされるとも考えられていない)当たり前のことになっている。
2010年8月24日 14:00
小田切博の「キャラクターのランドスケープ」
過去の記事
- 「クールジャパン時代」の終わり2011年5月25日
- 「わからない」という出発点2011年4月27日
- ヒーローはいつも間に合わない2011年3月22日
- ある「共感」2011年2月22日
- エロと暴力のマンガ、アニメ2011年1月26日