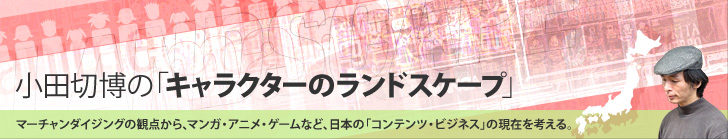「ぼくら」の再生産
2010年12月22日
(これまでの 小田切博の「キャラクターのランドスケープ」はこちら)
私は以前、『戦争はいかに「マンガ」を変えるか』(NTT出版、2007年)という「911」以降のアメリカンコミックスの変化を論じた著作の中で、村上知彦や米沢嘉博といった70年代後半から80年代にかけて登場したマンガ評論家たちに対して、共通の世代的な傾向を見出し批判したことがある。
これは伊藤剛が『テヅカ・イズ・デッド』(NTT出版、2005年)の中で彼らの言説を「ぼくら語り」と呼んで批判していたことを受けて書いたもので、批判しているポイントこそ異なるものの、伊藤も私も70年代後半から80年代にかけてのマンガ言説を「マンガ言説が変質していく転換点」と考える点ではほぼ共通していた。
しかし、私は最近日本における過去のマンガ言説を具体的に追っていく中で、自分のこの考えは誤っていたのではないかと考えはじめた。その反省の契機となったことのひとつに、村上や米澤らのほぼ二世代上の批評家である石子順造が、伊藤のいう「ぼくら語り」と見紛うテキストを書いているのを発見したことがある。
少し長くなるが、次の二つの引用を見てもらいたい。
要するにぼく(ら)の姿勢なりアプローチは、ぼく(ら)にとってマンガとは何であったかであり、同時に、そのようなマンガにとって、ぼく(ら)とは何であったか、である。むろんぼくたちは、マンガによらずとも、たとえば文学や映画によっても、自らを問い、語ることができただろう。しかしついにマンガ体験とでもいうしかない体験によって、そこで、ぼくらが受け取ったというよりは、発せざるえなかった何かを、あるいは発しようとしている何かを、ぼくらのもの--情況とのかかりの一部とするしかなかった、そしてそれだけだった、とぼく(ら)は思う。
(「あとがき」、石子順造、『現代漫画論集』、青林堂、1969年、P283〜284)
そのようなぼくらの眼中には「まんがと社会」や「まんがと戦後」や「まんがと文学」「まんがと映画」「まんがとTV」「まんがと思想」その他もろもろの、まんがと他の物を対立させて展開するまんが論など、入っては来なかった。ぼくらにとっては、まんがはまんがとしてそのまま社会であり歴史であり、あるいは社会や思想すらがぼくらのまえにはまんがとしてしか存在せず、そのなかで、自身がそれにどうかかわるかについて思いめぐらすしかなかったのだ。
(「まんが評論になにが可能か」、村上知彦、『イッツ・オンリー・コミックス』、廣済堂文庫、1991年、P330)
最初の引用は、石子が梶井純や権藤晋といった彼自身より一世代下の雑誌『ガロ』周辺の批評家達と創刊した漫画批評誌『漫画主義』掲載の論考を集めた論集のあとがき、二番目は70年代末に発表された村上のマンガ評論を集めた本のまえがきにあたる文章である。
一読してもらえばわかると思うが、ここで年の離れた二人の批評家は約十年の時間を挟みながらほぼ同じことを主張している。石子と村上はともに「ぼくら」にとって「マンガ」は共通体験であり、文学や映画よりも重要なのだ、といっているのだ。少なくともここでの石子は固有の読者共同体を前提にしているという意味で伊藤のいう「ぼくら語り」をおこなっていると思われる。
現在の読者にはあまり知られていないが、もともと先鋭的な美術評論家であり、最近では伊藤や夏目房之介から「マンガ表現論の先駆者」というかたちで再評価もされている石子順造という書き手は、疑いなく日本のマンガ言説史においては最重要な書き手の一人である。ただ、夏目や竹内オサムといった後発の世代の批評家からは「イデオロギー優先で読者としての感覚からずれている」という批判もあり、私自身はそれを知っていたため、その石子がこんなにずぶずぶに読者としての実体験、感覚によりかかった文章を書いているのを見てちょっと驚かざるを得なかった。
要するに「なんだよ、60年代から「ぼくら語り」はあったんじゃないか」ということなのだが、じつは同じ「ぼくらのものとしてのマンガ」が語られているようでいて、この石子と村上における「マンガ」は重なりながらもかなり違ったものを指している。
村上のいう「マンガ」は現在のマンガのイメージにつながる少年誌や少女誌のマンガだが、石子をはじめとする『漫画主義』の書き手にとっての「ぼくらのマンガ」は明確に貸本劇画とその延長にある劇画を指している。そして、当時は「子ども漫画」と呼ばれていた村上のいう「マンガ」は、石子らからはむしろその「商業主義的な性格」によって批判的に取り上げられていた。
そこまで見ると先の夏目や竹内の石子批判の理由もわかってくる。
おそらく夏目や竹内のいう「読者としての感覚からのズレ」とは、「(自分たちの世代の)読者としての感覚」から石子らのマンガ観がずれている、ということなのだ。石子らは自分たちの貸本劇画読者としての感覚から子ども漫画を批判し、そのような石子たちの姿勢をその子ども漫画の読者である夏目や竹内が批判する、という図式をそこに見ることが可能だ。
伊藤剛は『テヅカ・イズ・デッド』で村上や米澤が90年代以降「マンガがつまらなくなった」と書いていることを批判し、その原因を彼らが「現在の多様なマンガ作品の存在を肯定的に捉えられなくなった」ことに置いているが、ここにも同様の「読者としての感覚のズレ」を見ることができる。多様化し、マーチャンダイズ化した現代のマンガが村上らの「ストーリーマンガ」こそマンガであるとする世代からは「つまらなく」見え、伊藤や東浩紀といった現在の批評家たちがそれに対して「現在の読者の実感」として「萌え」のような記号的なキャラクター消費の正統性を訴えている。
だが、こうした議論は不毛ではないだろうか。
これは最初に書いた私自身の見方への自省も含めていうのだが、先行する世代の「マンガ観」の内実を見ずに、それを次の世代が自分たちの実感ベースの「マンガ観」で否定するのでは、結果的に新たな「ぼくら」を再生産しているだけ、ということになりかねない。
重要なのは、先行する「マンガ観」をキチンとその背景を含めて把握した上で位置付け、歴史として積み上げていくことだ。そのための前提として、村上や米澤らの世代の言説を転換点と看做すのではなく、「読者としての感覚」によってマンガを語ることに価値を見出すことで「ぼくら」が再生産される構造、この構造を自覚することこそがまず必要なのではないか。
とりあえず私自身はいまそんな風に考えている。
小田切博の「キャラクターのランドスケープ」
過去の記事
- 「クールジャパン時代」の終わり2011年5月25日
- 「わからない」という出発点2011年4月27日
- ヒーローはいつも間に合わない2011年3月22日
- ある「共感」2011年2月22日
- エロと暴力のマンガ、アニメ2011年1月26日