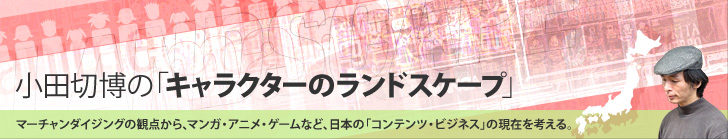「マンガの神様」からの宿題
2010年11月24日
(これまでの 小田切博の「キャラクターのランドスケープ」はこちら)
手塚治虫の生前最後のインタビュー集として石子順を聞き役とした『漫画の奥義 作り手からの漫画論』(2007年、光文社)という本がある。
この本の冒頭「〔前口上〕漫画とは何か」において、手塚は「マスコミや評論家の人たち」が「漫画とは何か」がよくわかっていないことを批判し、「漫画の世界はそんなに漠然としたものではなく、もっと範囲も狭いし、非常に限定された世界の中で、限定された作品が生まれているものなのです」と指摘している。
皮肉なことに、同書は自身を含む戦後マンガの「限定された世界」を具体的に語る直前で手塚の入院によって中断しており、はっきりしたマンガ観がけっきょくは示されないまま終わっているのだが、ここで手塚が提起している「漫画とは何か」という問題は、このインタビューが収録されてから二十年以上が経つ現在でも、依然として「漠然とした」ままである。
同書の中で手塚は、自身を北沢楽天と岡本一平にはじまる「昭和漫画史」に連なる存在と規定している。第二次大戦直後の一時期、日本には「漫画のルネサンス」と呼ぶべき時代があり、現在の日本の「漫画文化」の原点はそこにあるのだ、という旨の指摘をしている。
後者についても今後調査、研究されるべき重要なポイントを示唆するものではないかという気がするのだが、現在直接的に問題にせざるを得ないのは前者だろう。
手塚自身も同書やそれ以前のいくつかのエッセイで指摘しているが、現在のマンガ批評や研究の多くは「マンガ」を手塚以降のストーリーマンガを指すものと無意識に規定しており、ここでいう「昭和漫画史」のような視点自体を持っていない場合が多い。
もちろんこれは「多く」であって「すべて」ではないのだが、そのこと自体が現在におけるマンガ論の混乱の原因になっている。
時代によるマンガ観の相違については前にも書いたことがあるが、手塚のいう「昭和漫画史」を前提にする世代のマンガ観、たとえば清水勲『漫画の歴史』(1991年、岩波書店)などで示されているそれと、伊藤剛『テヅカ・イズ・デッド ひらかれたマンガ表現論へ』(2005年、NTT出版)などで示されている現在のマンガ批評におけるそれとでは、一見同じ「マンガ/まんが/漫画」という言葉を使いながら、それぞれが準拠しているマンガ観は微妙どころではない異なり方をしている。
一コママンガの研究者である清水は、あくまで「滑稽な絵」としての部分に「マンガ」のアイデンティティーを見出している部分がある一方、ストーリーマンガへの関心は薄い。コマ割りされたストーリーマンガこそが「マンガ」であるという前提に立っている伊藤は、事実上「一コママンガ」をその分析の対象としていない。
もはやそこではそれぞれが前提にしている「マンガ」そのものが異なっているのである。
私はここでどちらのマンガ観が正しいとかすぐれているといったことをいいたいわけではない。たとえば清水と伊藤のあいだで直接「マンガ」について話し合われたとして、そこでは本当に話が通じているのかが疑問なのだ。
実際には全然違ったものを見ていながら、それが同じ言葉を介しているがゆえに、なんとなくお互いに話が通じているような気になってしまう。
ここでいう「マンガ論の混乱」というのはそのようなものなのだが、「マンガの神様」からの「漫画はそんなに漠然としたものではない」という指摘は(その「正解」が示されないままになっていることを含め)相当辛辣で大きな宿題なのではないかという気がしている。
小田切博の「キャラクターのランドスケープ」
過去の記事
- 「クールジャパン時代」の終わり2011年5月25日
- 「わからない」という出発点2011年4月27日
- ヒーローはいつも間に合わない2011年3月22日
- ある「共感」2011年2月22日
- エロと暴力のマンガ、アニメ2011年1月26日