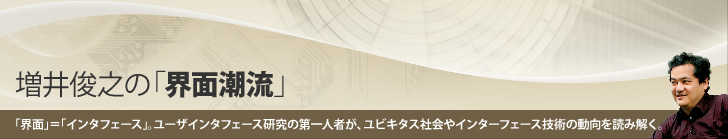第25回 ユーザは使いよう
近年のユーザインタフェース開発では「ユーザ中心設計」(User-centered Design)を行なうことが常識になっています。設計の初期段階からユーザの欲求についてよく検討し開発を行えば、本当にユーザにとって使いやすいシステムを開発することが可能になります。
2008年7月22日 08:00
第24回 イメージが重要
そもそもWebが流行したきっかけは、Mosaicで画像が表示されるようになったことであり、文字しか表示されないブラウザしかなければ、これだけWebが流行ることはなかったでしょう。いくら優れた内容でも、テキストだけのWebページは魅力に欠けるものです。
2008年7月 8日 08:00
第23回 ネットコピペ
ブラウザのブックマーク機能は、ちょっと使うには便利な機能なのですが、本格的に活用しようとするとすぐにメニューがあふれてしまいます。また、異なるブラウザやマシンでブックマークを共有することもできません。ブラウザのブックマーク機能は実際にはあまり有用なものではありません。今回は、このような問題を解決する方法をいくつか。
2008年6月 2日 08:00
第22回 大きなデータを眺める
情報視覚化の研究は、1990年頃からXerox PARCなどで盛んになりましたが、当時は高速3次元表示が可能な計算機が高価だったり、ぼう大な量のデータがあまりなかったりで、このような研究を行なえる場所は限られていました。20年を経て、ようやく本格的な応用が見えてきたようです。
2008年5月16日 08:00
第21回 流れる情報と留まる情報
世の中の様々な情報は、いつでも参照できるストック型情報と、リアルタイムに流れてくるフロー型情報におおまかに分類することができます。ネット上の様々なコミュニケーションシステムはフロー的かストック的かのいずれかであることが多く、両方の特徴を備えた便利なシステムはまだ出現していないようです。
2008年3月26日 22:20
第20回 日本語でおk
これまで様々な「日本語プログラミング」が提案されてきましたが、文の構造と計算機処理の流れを一致させやすいといった日本語特有の性質を充分活用すれば、普通の英語的なプログラミングよりも良い結果が得られる可能性があるでしょう。
2008年3月 3日 01:00
第19回 存在の証明
Web上の情報共有サービスは今後もどんどん増えてくることでしょう。現在のところ、共有された情報自体を楽しむという単純なサービスがほとんどですが、データの存在の証明や重要度の計算といった新しい応用が増えてくることを期待したいと思います。
2008年2月15日 10:00
第18回 発見人生
財力があっても工夫が足りなければ満足することはできませんが、金が無くても毎日新しい発見があれば楽しく満足した暮らしができるはずです。楽しく面白い人生を送るためには財力よりも発見力が重要だと思われます。
2008年1月26日 15:32
第17回 検索と入力の素敵な関係
「入力」と「検索」は全く別物と考えられているのが普通です。実は検索と入力はほとんど一体のものであると考えると両者の関係がすっきりします。長い目で検索と入力の融合の工夫について考えていきたいと思います。
2008年1月11日 01:00
第16回 知識の呪い
自分が作った機械を世の中に普及させたいのであれば、自分以外の誰もが使えるようにする必要があります。他人の嗜好や考え方を充分想像することができなければ、自分だけしか使えないシステムしか作ることはできないでしょう。
2007年12月21日 11:00
増井俊之の「界面潮流」
過去の記事
- 第55回 ものづくり革命2011年5月16日
- 第54回 マイIME2011年4月15日
- 第53回 NFC革命2011年3月10日
- 第52回 自己正当化の圧力2011年2月10日
- 第51回 縦書き主義2011年1月17日