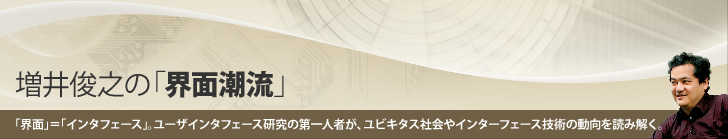第45回 台所コンピューティング
「エクストリーム・アイロンがけ」というスポーツがあります。エクストリームな環境で計算機を利用する「エクストリーム・コンピューティング」という競技も可能かもしれません。高山や極地まで行かなくても、計算機にとってエクストリームな環境があらゆる家庭に存在します。
2010年7月14日 14:30
第44回 例示システムの逆襲
Web上のサービスが増えてきた結果、多くの仕事をブラウザ上で実行できるようになってきました。Webブラウザ上での作業が増えてくると、様々なサイトを利用してルーチンワークを行なう機会が増え、ブラウザで上の作業を自動化したくなることが多くなると思われます。
2010年6月17日 14:30
第43回 圧縮的情報管理
ジョーク好きの2人が列車に乗り合わせた。だがこの2人はジョークを言い飽きてしまっていた。「ジョークをいちいちしゃべるのは面倒だから、ジョークに番号を付けて番号で呼ぶことにしよう」A:「8番」B:「ははは」B:「25番」A:「ははは」こう繰り返している内にAが……。
2010年5月12日 14:30
第42回 脳と仮装
心理学者のPaul J. Silviaの「How to write a lot」という本によれば、文章を沢山書こうとする人は執筆する時間を決めて必ずそれを守ることが重要で、それ以外に有効な方法は存在しないのだそうです。
2010年4月14日 16:30
第41回 変化の認知
人間は時間的な変化の認知が得意ではありません。変化の可能性に気付かず、一時的な状態のことを定常状態だと勘違いしてしまうことがよくあります。何かが一度うまくいったとき、それが普通だと勘違いしてしまうと「待ちぼうけ」のような失敗をしてしまいます。
2010年3月 8日 16:00
第40回 そもそもの台頭
各種のカードはそもそも個人認証ができれば不要になるはずです。そもそも番組や音楽を自由に楽しむことができるならば、リモコンは全て不要になるはずです。コミュニケーションが円滑に行なわれるのであれば、手紙を投函するといった手間はそもそも不要なはずです。
2010年2月 9日 19:00
第39回 名前の効用
人間社会では、様々なものを識別するのに「名前」が利用されています。計算機の利用やコミュニケーションにおいてもなんらかの名前を使うのが当然だと考えられていました。しかし、これらを扱うのに本当に名前が必要なのか、実は疑問です。
2010年1月13日 16:40
第38回 ユーザ評価の落とし穴
システムの開発時にユーザ評価が重要であることは間違い無いのですが、ユーザ評価結果を重視しすぎると問題が出ることがあります。最近はユーザ評価を重視しすぎることに関して疑問を感じる研究者も増えているようで、Bill BuxtonとSaul Greenberg、MITのHenry Liebermanも問題を提起しています。
2009年12月16日 11:00
第37回 安定感を求めて
割れた窓ガラスが放置されているような地域では治安の悪い雰囲気が定常化して犯罪が増えるが、小さな犯罪もきちんと取り締るようにすれば意識が変化し、結果的に大きな犯罪も減るという割れ窓理論という考え方があります。
2009年11月10日 13:50
第36回 手品とインタフェース
奇術や手品は人間の錯覚や勘違いを最大限に利用したエンターテインメントです。人間は錯覚や勘違いの固まりですから、突然何かが変化しても気付かなかったり/慣れたものを見逃すことが多かったり/手品の達人は観客の目前でも易々とイリュージョンを見せることができ、観客はそれを見て驚き楽しむことができます。
2009年10月14日 13:40
増井俊之の「界面潮流」
過去の記事
- 第55回 ものづくり革命2011年5月16日
- 第54回 マイIME2011年4月15日
- 第53回 NFC革命2011年3月10日
- 第52回 自己正当化の圧力2011年2月10日
- 第51回 縦書き主義2011年1月17日