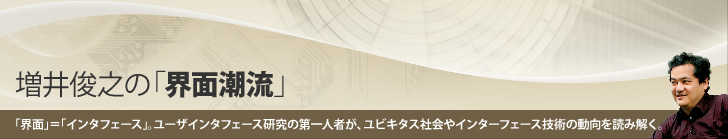第35回 覗き見対策
パスワードを使って計算機やWebサービスにログインするとき、パスワードは「****」のように伏字で表示されるのが普通です。ところがユーザビリティの専門家であるJacob Nielsen氏が突然、自分のブログで「パスワード入力の伏字は有害である」と言いだしました。
2009年9月15日 17:00
第34回 Webでお絵描きメモ
テキスト入力手法の進化が頭打ちになってきた現在は、画像や手書きメモを活用する方法をもっと追及するべき時代なのかもしれません。楽々ビジュアルなメモをとる方法をさらに追及していきたいと思っています。
2009年8月11日 10:00
第33回 電子工作再発見
個人的に重要な情報は今のところネットで検索することはできません。「自宅の戸締まりはきちんとしているか」「冷蔵庫にビールが冷えているか」といった大事な情報をGoogleは教えてくれません。しかし、ちょっとした電子工作をすれば、このような情報にアクセスすることができるようになります。
2009年7月14日 14:00
第32回 マクロで楽々HTML
Cのプログラムでは、定義された規則に従ってプログラム中の文字列を別の文字列に置き換えるマクロ機能を利用することができます。文章を書くときにもこのようなマクロ機能が使えると便利です。変更したくなったような場合でも、定義部分だけ修正すればよいことになります。
2009年6月 8日 14:00
第31回 安全と安心
絶望先生は、Suica改札を通ったとき、あらゆるカードがスキミングされたと思って絶望していたものです。寺田寅彦は浅間山の噴火を見ながら物事を正当にこわがるのはむずかしいと述べています。人間の心理についてよく考えつつ、安全と安心を両立させる技術を追及していく必要がありそうです。
2009年5月11日 13:00
第30回 スクローリングの小細工
スライダやスクロールバーのようなGUI部品は広く便利に使われていますが、これらの由来や発明者についてはあまり知られていないようです。スクロールバーのような動きをするものは現実世界に存在しませんから、誰がどのようにしてこのようなGUI部品を発明したのかは興味深いところです。
2009年4月24日 14:00
第29回 誤魔化す!技術
「誤魔化す」という言葉には悪いイメージがありますが、「情報隠蔽」というと多少聞こえが良くなるかもしれません。森の中に木を隠すという記事で、普通の画像やテキストの中に秘密情報を隠すステガノグラフィーという技術を紹介しましたが、これは内容を誤魔化すことにより秘密を守る技術の一例といえるでしょう。
2009年1月22日 18:00
第28回 不在問題
何かが存在することを示したり存在に気付いたりすることは簡単ですが、存在しない事物をうまく扱うことは簡単ではありません。シャーロックホームズの白銀号事件では、事件発生時に犬が吠えなかったという事実に気付いたホームズが、それを手掛かりに事件を解決しました。
2008年12月 5日 11:30
第27回 なぞなぞ伏字
公開すると問題があるかもしれない名前などを「伏字」にしたいことがあります。そもそも何も公開しなければいいのかもしれませんが、友人などにだけわかる形で情報を公開したいこともあります。このような場合、伏字を解読する方法を用意しておけば、隠れたメッセージを友人などにだけ公開することができるようになります。
2008年11月21日 16:30
第26回 森の中に木を隠す
暗号化したことがわからないように秘密データを普通のデータの中に埋め込む手法をステガノグラフィーと呼びます。普通の暗号と異なり、データが隠されていること自体が自明でないため、解読の危険に晒される危険が少ないと考えられています。
2008年9月12日 13:10
増井俊之の「界面潮流」
過去の記事
- 第55回 ものづくり革命2011年5月16日
- 第54回 マイIME2011年4月15日
- 第53回 NFC革命2011年3月10日
- 第52回 自己正当化の圧力2011年2月10日
- 第51回 縦書き主義2011年1月17日