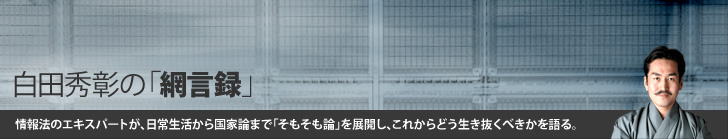第四回 美と規範 II
2007年6月 6日
ここで話は、遡る。
よく知られた話だが、かつて芸術家たちは、社会階層的には職人に分類されていた。さらに、職人のうちでもかなり科学者あるいは化学者に近い位置付けにあった。画家は、様々な鉱物や諸素材の性質や化学反応に関する知識をもち、自然界に存在する様々な素材を用いながら、鮮やかで自由な発色をもち長期間退色しない絵具の開発を目指した。さらに彼らは、構図においては、人間の視覚の傾向と幾何学を組み合わせることで、仮想的な遠近感を演出し、光学に関する知識を用いて三次元空間の諸物体への光の影響を研究した。彫刻家や建築家は、数学を用い力学的構造学的に均整の取れた建造物を設計し、さらに我々の感性に美しさと安定感をもたらす原則の発見に力を注いだ。こうした「科学者としての芸術家」の例としては、レオナルド・ダ・ヴィンチが挙げられる。月並みな知識で申し訳ないが。
さらに遡って、ギリシャ、ローマの古典期においては、哲学の一つのテーマとして「美」とくに「普遍的な美」についての考察と実践が行われていた。私達の現実の裸体は、ギリシャ彫刻のようには美しくない。さらに我々が100人集まってその裸体の平均をとったところで、美しい裸体にならないだろう。仮にその100人が現代ギリシャ人であったとしても[*1]。 ではなぜ、ギリシャの彫刻家達は、古代から現代にまでいたる人々に受け入れられる「美」を発見し得たのだろうか。彼らはどこにも存在しない、人間の肉体の理想形を単に偶然に生み出したのだろうか。そしてそれを「制度」として私達が無批判に継承する中で典型としての地位を獲得したのだろうか。
古典的な美や普遍的な美の概念が単なる制度であるという、社会学的批判がありうることは承知の上で私はあえて言う。ギリシャ時代から近代に至るまで、視覚的作用により我々が「美」と感じる「何ものか」あるいは「何らかの効果」を探求し、それを典型として抽出しようという強い動機が、美術あるいは美学の中に一貫して存在し、いくつかの作品においてそれに成功したのだと。そして抽出された典型は規範として後世の芸術家たちに継承されたのだと。こうした考え方は、まさに「アカデミック」な芸術のあり方に他ならない。そうした典型は、多くの場合、自然観察から発見された物理的原理原則や、数学的な考察や検討から発見された原理原則と調和的に説明し得た。その例としては、黄金比を巡る議論を参照していただければよいだろう。美術は、感性の学ではなく総合科学として存在していたのだ。
故に、芸術家の養成機関においては、古代から積み上げられてきた「美」に関する典型と規範が維持、洗練、伝達されていた。そうした長い積み重ねが Classic として普遍的な美の概念を作り上げてきたのだ。もちろん、私は「普遍的な美」という概念それ自体が批判されるべきだという主張があることは承知の上で、それを評価していることを付言しておく。こうした「普遍的な美」の概念は、実はアカデミックな絵画や理論を乗り越えたはずのいわゆる「現代美術」の基礎であり、それらの諸作品の中にも容易に発見されうる、という議論もある[*2]。さらに現代美術は、アカデミックが掬い上げそこなった「存在可能性のあったもう一つの普遍的な美」を目指して実践されているのだろうと思う。
ここで、まとめよう。近代に至って開始された多様な諸様式・諸作品は、古典的な普遍性のある美の概念を基礎として、そこからの変容の距離によって美的空間[*3]における互いの位置関係を測れたのだ。確かに「普遍的な美」は「多様な美」の中の一つかもしれないが、少なくとも、「普遍的な美」が固定点として機能しなければ、あらゆる諸様式・諸作品はすべてが均質な美的空間に基準なく散在するだけになってしまう。私個人の意見としては、物理的、数学的、そして人間の認知能力的に、普遍的に「美」と感じられる何ものかが確固として存在すると考えている。
さて、ここで再び現代に戻る。
かように純粋美術には、哲学的に深遠な要素があるのだと私は思っているのだが、どうも当の純粋美術を実践している学生さんたちには、そうした意識がないのではないかと私は感じるのだ。直接的に彼らと接する限り。
単に器用に絵具をキャンバスに置き、表面的に何事か人目を引く画像を描くだけであるなら、たぶん美術*大学*は必要ない。商業美術を主とするデザイン領域であれば、そうした深遠な「美」に関する哲学が見失われてしまったとしても、市場調査の手法と感覚刺激に対する人間の反応を指導原理にしながら、制作を進めていくこともできるし、その結果として、デザインの領域には「ある時代の一般的な嗜好なり空気のような何ものか」が表現されていく。でも、もし純粋美術が哲学的な探求を失ったら、まったくの混乱と迷走に陥るのではないかと私は考えている。そして、先に卒業制作展の感想でも述べたように、どうもそういう状態に陥っているのではないかと思っているのだ。
* * * * *
*1. 多数の人間の顔のデータをどんどん平均化すると、まさに平均的な顔が作り出されるのだが、その顔は、どこかで見たことがあり、我々が好感を持ちやすい顔になるらしい。我々はやはり平均的なものにも「美」を見出すのだろう。「平均顔ギャラリー」
*2. もっとも典型的な例としては、一般庶民にとって「ワケのワカラナイ絵画」の筆頭であるだろうパブロ・ピカソが挙げられるだろう。彼が、若き日にデッサンの天才と呼ばれていたこと、初期には高水準の古典的な作品も存在すること、さらに中期後期のワケノワカラナイような作品についても、その構図の均衡について、古典的な理論で説明しうることから、彼が美術理論をまったく無視して創作活動していたわけではないことがわかる。
*3. うーん... 美を目的とする表現を包含する集合が存在するとして、そこに様々な評価軸を設定しうる概念的な空間を指す表現、と本論においては定義させてください。私の知識ではどうにも表現しようがないので、造語してしまいました。
白田秀彰の「網言録」
過去の記事
- 最終回 暇申2007年10月 3日
- 第廿回 和装 IV2007年9月26日
- 第十九回 和装 III2007年9月19日
- 第十八回 和装 II2007年9月12日
- 第十七回 幕間 III2007年9月 5日