ILM幹部、デジタルドメインCEOから人材育成へ:スコット・ロス氏インタビュー
2009年12月24日

スコット・ロス氏は、エンターテインメントおよびテクノロジー業界で30年以上のキャリアを持ち、デジタルメディアの黎明期から第一線で活躍してきたカリスマ的存在だ。80年代には、ジョージ・ルーカス監督が立ち上げた特殊効果・視覚効果スタジオIndustrial Light and Magic(ILM)社のゼネラルマネージャー、関連企業LucasArts Entertainment Group社の副社長を歴任し、1993年、現在『アバター』が公開中のジェームズ・キャメロン監督らとともに視覚効果専門のDigital Domain社を設立。同社の会長兼CEOとして約20年にわたり、ハリウッド映画の超大作・話題作に関わってきた。
同社を退職してからはプロデュース業などを手がけ、今年7月には総合的なアートとデザインの大学、Savannah College of Art and Design(SCAD)の映画・デジタルメディア・舞台芸術学部エグゼクティブ・アドバイザーに就任。先週横浜で開催されたシーグラフアジア2009で基調演説を行うため来日したロス氏に、インタビューする機会を得た。
――最初に、ロスさんは少年時代、学生時代をどのように過ごしていたのか教えていただけますか。
スコット・ロス氏(以下敬称略):私は今58歳で、村上春樹氏と同年代なんです。つまり1960年代に十代を過ごし、まずローリング・ストーンズやビートルズ、ザ・フーといったロックススターに憧れ、自身でもサックスや歌でバンド活動をしていました。高校を卒業するとき、徴兵されベトナム戦争に送られるのを避けるため大学に進むことにしましたが、楽譜の読み書きといった楽典の素養がなかったので、次に好きだった映画の課程を選んだのです。学部ではフェデリコ・フェリーニやフランソワ・トリュフォーといった監督たちの作品を鑑賞し、批評分析するといったことをしていました。
――米国の映画よりも欧州の映画を好んで観ていたのですか?
ロス:米国の映画はひどかった(笑)。その頃はジョン・ウェイン主演のものや、ミュージカル作品といったものばかり。一方で欧州の映画は私をとりこにしました。それに日本映画。私は黒澤明の大ファンになりました。
――映画業界に入るまでの経緯はどのようなものだったのでしょう?
ロス:私の興味の対象は常にエンターテインメント全般にありましたが、ミュージシャンだったこともあり、特に音響関連技術のスキル、具体的にはPAシステムの操作などを得意としていました。当時は家が裕福でなかったこともあり、手っ取り早くお金を稼ぐ必要があったため、音響エンジニアとしてプロのバンドのコンサートツアーに同行するようになりました。最後の頃はマイルズ・デイビスのバンドのツアーに同行し、ジャズが大好きになりましたね。こうして音楽業界に足がかりを得たあと、ミュージシャンの映像を撮影したり監督したりといった仕事にシフトし、そうこうするうちにポストプロダクション会社のマネージャー職に就きました。
当時の80年代前半はちょうど、MTVが登場し、音楽プロモーションビデオが普及した時期です。私はそれまで培ってきた音楽的嗜好と音響技術、映像の知識とスキルをすべて組み合わせることができるPV制作の仕事を得て、最高にハッピーでした。この頃に、17歳でPVを作っていたデヴィッド・フィンチャー[後に『エイリアン3』『セブン』『ベンジャミン・バトン 数奇な人生』などを監督]に出会いましたが、彼が当時勤めていたのがILMでした。「ILMで仕事をするというのはすごいことだな」と思ったものですが、その2年後にILMの幹部からヘッドハントされ、同社の経営に携わる職を得たというわけです。
ここでパーフェークト・ストーム[複数の重要な事柄が局所で同時に発生すること]が起きました。それまでに私たちの部門が制作していたビデオは、技術的にまだ映画に使える状態ではありませんでした。その当時新しくできたばかりの、グラフィックス専用コンピューターを手がけるSilicon Graphics社に友人ができ、また、後にILMから独立してPixarとなる部門がフィルムスキャナーを開発しました。ほかにも、Quantel社の中間ユーザーインターフェースや、Celco社のデジタルフィルムレコーダーの開発が重なり、ここに来て初めて、フィルムで撮影された映像素材をコンピューターのソフトウェアに取り込み、処理を加えてから出力するというシステムが実現したのです。この時からデジタル映像制作の歴史が始まりました。
――後にDigital Domain(DD)社を共同で設立することになるジェームズ・キャメロン監督と、 スタン・ウィンストン氏[『ターミネーター』シリーズや『エイリアン2』などの特殊効果・視覚効果を担当]とはこのILM時代に知り合ったのでしょうか。
ロス:キャメロン監督と出会ったのは、ILMが『アビス』のVFXに関わったときのことです。ILMは同作に登場する[液状の触手が人間の顔などに変形する]エイリアンのクリーチャーを担当しました。この技術は後に『ターミネーター2』の「T-1000」[液体金属アンドロイドのモーフィング]に発展します。なお、スタンとは後にキャメロン監督から紹介されて知り合いました。
――どのようないきさつで独自のVFXスタジオを興すことになったのでしょう?
ロス:私の情熱は常に、コンテンツを制作することに向けられていました。自分は技術屋というよりは、クリエイティブな人間だと思っています。ILMには才能豊かな人材が大勢いて、私は映画を作りたかったのですが、ジョージ[・ルーカス]は『ハワード・ザ・ダック』の失敗のあとでそれを望みませんでした。コンテンツを制作するためにはILMを離れる必要があると判断し、DD社を設立したというわけです。時期的には数年前になりますが、Pixarもまた[スティーブ・ジョブズ氏が買い取って]ILMから独立してCGアニメ映画会社への道を歩み始めました。ILMという巨大な母船から、いくつもの映像制作会社が旅立っていったのです。
――DD社時代に関わってきた作品で印象に残っているものは?
ロス:最初に手がけたプロジェクトは『トゥルーライズ』です。多数のVFXが使われ、キャメロン監督の作品として当然、高いハードルが設定されていました。とにかくコンピューターもソフトウェアも何もない、ゼロからのスタートです。設立者の3人とIBM社が資金を出し合って必要な制作環境を整え、150人ほどのスタッフをまとめて、9ヵ月かけ――納期に間に合うか不安を抱えながら、私自身何日も徹夜して――あの効果を作り上げたのです。苦労した甲斐があって、同作はアカデミー賞[Best Effects/Visual Effects部門]にノミネートされました。
一番苦労したのはやはりキャメロン監督の『タイタニック』。最も難しいチャレンジになったのは、日中に沖に出たタイタニック号の全容を空撮ショットで描くシーンです。あのショットはミニチュアの船――ミニチュアと言っても、この会議室の4倍くらいの大きさですが――を使い、海面と船上の人間はすべてデジタルで制作しました。それぞれを重ねて1つの映像にまとめるという作業がとにかく大変でしたね。
――『デイ・アフター・トゥモロー』も津波などの驚異的なVFXが使われ、同作に参加したDD社の日本人クリエイター、坂口亮氏も日本のメディアで紹介され話題になりました。
ロス:『デイ・アフター・トゥモロー』はおそらく私がDD社にいた時期でベストの数本に入るでしょう。DD社はそれまでの作品を通じて、水の表現に関してエキスパートになっていました。リョウ・サカグチについてはいい話があります。私が日本の専門学校――都築総合学園の「スコット・ロス デジタルスクール」――に関わっていたとき、毎年1人か2人、特に優秀な学生をインターンとしてDD社に招いていました。サカグチは最初のインターン生でした。ただし私が日本で初めて彼に会ったとき、あまりに寡黙だったため「彼は米国ではうまくやれないんじゃないか」と懸念したのですが、サカグチを指導していた教授は、彼はとにかく優秀なので推薦すると強く主張しました。そして実際、彼は渡米してから1年以内に、教授の言葉が正しかったことを証明しました。サカグチは私が出会った中で最も優秀な人物ですね。その後DD社に就職してからも順調にキャリアを重ね、流体力学シミュレーションの科学的な達成が認められてアカデミー賞[2008年の科学技術賞]を受賞したのです。
――次に「デジタル・ドメイン後」の話題に移りますが、VFX制作会社のトップから、現在の教育機関の役職、Savannah College of Art and Design(SCAD)の映画・デジタルメディア・舞台芸術学部エグゼクティブ・アドバイザーに転身したのはなぜでしょう?
ロス:いくつか理由があります。まず、当時までのキャリア、ポジションで私がVFXの領域でできることはすべてやり尽くしたと感じていました。この分野でもう私自身がチャレンジできることはないだろうし、正直なところ仕事に疲れてもいました。私はDD社の権利を売却することにして、自分で好きなことを選べる状況になりました。
やりたいことは主に2つありました。第1は、意味のある映画を作ること。言ってみれば、私はこれまで「本当にひどい映画のベストな部分」(the best parts of really bad movies)に関わってきました。だからそれ以降は、人が死んだり破壊や爆発が目玉になるような映画ではない(笑)、重要な作品に関わりたいと思ったのです。そこで、いくつかのプロジェクトを進めて、時には脚本に関わり、時にはプロデューサーとして資金を集めたりしてきました。
ただし、そうした仕事をして過ごすのは週に20時間程度です。私はゴルフが得意なわけでもないし、何かほかのことをする時間がまだあります。そして同時に、これまでのキャリアで得たスキルを、若い学生たちに還元するということも、私がやりたいことの1つでした。ここでまたパーフェークト・ストームが起きました。高校の同窓生と40年ぶりに集まる機会があり、かつて私と一緒に働いてアカデミー賞を受賞し、現在はSCADで教えている男が、私に一度学生を教えてくれないかと頼み込んできました。そこで同校のウェブサイトをチェックしたところ、私が40年前に大好きで、それっきり会っていなかった女の子が教授になっていることを知ったんですね(笑)。そこで私はすぐに旧友に連絡をとり、「講義するよ」と答えました(笑)。
そうしてSCADに赴いたわけですが、もうすぐ60歳になろうという彼女に再び恋をすることはありませんでした。そのかわり、私は学校に恋をしたのです。もし私が若いときにSCADがあれば、まさに行きたいと思ったであろう素晴らしい学校でした。これまで見た中でも最も幅広い分野が集められたアートスクールです。学術研究よりも、実地での制作や創作が主体の学校で、入学して1年目からすぐに、最先端の機器を使いながらプロジェクトに携われるのです。
また、SCADの学長からは、新たに香港にキャンパスを開校する[2010年秋開校予定]手伝いをしてほしいと頼まれました。私はこれまで2つのVFXスタジオの時代に幾度となくアジアを訪れていて、アジアは個人的に居心地のよい場所でもあるので、願ってもない話だと快諾したのです。香港に常駐するわけではありませんが、米国と頻繁に往復することになりそうです。もし香港で撮影する映画のプロジェクトが資金獲得できれば、現地に引っ越すかもしれませんけどね(笑)。SCADのサバンナ校ではすでに四半期にわたって講義を持ちましたが、この形なら香港でもできそうなので、年に3ヵ月くらいは教えに行くことになるかもしれません。
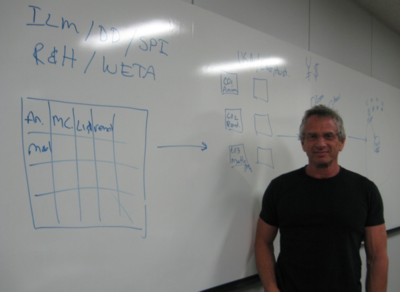 ――シーグラフ2009のセッションではSCADを代表して講演されますが、どういった内容になるのでしょう。
――シーグラフ2009のセッションではSCADを代表して講演されますが、どういった内容になるのでしょう。
ロス:プレゼンで話す中身は実に単純で、今あるVFXやアニメーションの業界は、5年後には同じ形では存在していないということです。現在は英米とオセアニアの英語圏にVFXのトップ5社――ILM、DD、Sony Pictures Imageworks(SPI)、R&H、WETA――があり、各社の仕事の形態は、1つボックスの中にすべて――アニメーション、モーションコントロール、ライティング、レンダリング、モデリングなど――が収まっているという状況です。これがやがて移行し、A社がアニメーション、B社がレンダリングといった具合に分業体制で映画が作られるようになります。
さらに先に進むと、世界中で制作業務が細分化し、南米やアジアなどを拠点とするクリエイターたちもインターネットを介して協業できるようになるでしょう。こうした変化が5年後ぐらいには起きて、会社にスタッフが集まって仕事をするのではなく、個々のクリエイターが映画制作に直接関わる形態になるということです。これは個人にとって大きなチャンスです。ロサンゼルスに移住しなくても、自分の望む場所で映画のVFXができるのです――たとえば岐阜県の飛騨高山でも(笑)。SCADでは学生たちに、このような近い未来に起こる制作環境の変化について学んでもらい、そうした新しい環境に対応できるスキルを身につけてもらおうと考えています。
――日本の映画、コンテンツについてコメントをいただけますか?
ロス:私は宮崎駿監督の大ファンなんです。それに以前は、『ウルトラマン』や『Astro Boy』(鉄腕アトム)、『GHOST IN THE SHELL』[『攻殻機動隊』押井守監督]なども好きでしたね。宮崎映画については、米国で[劇場公開されるまでになったとはいえ]まだそれほど大勢から受け入れられていないのが個人的にとても残念です。たとえば、『ハウルの動く城』は確か日本で2億ドルくらいの大ヒットだったと思いますが、米国だとその100分の1程度でした。
――デジタルメディアの将来についてはどのように予想していらっしゃいますか。
ロス:携帯端末にしろ、家庭のテレビにしろ、ディスプレイはもっと大きくなるでしょう。現在でさえも、コンテンツの作り手は、どういうサイズ、形状のメディアでそれらを提供するかについて十分に考える必要があります。映像に関しても、単にテレビだけでなく、ウェブサイトで配信したり、特定の端末に特定の目的を持って配信することを考慮すべきです。できるなら長生きして『ストレンジ・デイズ』[ジェームズ・キャメロン脚本・製作のSF映画。個人の五感の体験を「デジタル・ドラッグ」に記録して、他人が追体験できるという未来技術が登場する]の世界が実現するのを見てみたいと思います。まあ似たようなことは60年代にも体験できたけど、違法でしたからね(笑)。
――最後になりますが、日本のクリエイターやクリエイター志望者たちにメッセージをいただけますでしょうか。
テクノロジーに偏って考えるのではなく、心から出てくるものをより大切にしてモノ作りに向かってほしいと思います。人間には主要な2つの臓器、心臓と脳があります。私たちは脳ばかりを使いすぎて、あまり心を使わなくなっています。「心を伝えるコンテンツ」を作ることを目指してほしいですね。
[関連リンク]
・Savannah College of Art and Design(SCAD)
・Digital Domain
・シーグラフアジア2009
高森郁哉の「ArtとTechの明日が見たい」
過去の記事
- 最後に、オススメの映画を何本か2011年5月31日
- 放射性廃棄物を巡る問いかけと印象的な映像:『100,000年後の安全』2011年4月15日
- マイケル・ムーアに原発問題を映画化してほしい2011年4月11日
- 震災と映画業界:公開延期と、「自粛解除」の兆し2011年3月29日
- 「SF系」、地味に現実へ浸食中2011年2月28日

